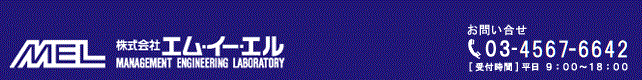社長のコラム
着眼大局、着手小局
代表取締役社長 石黒仁司
「我々が行動可能なのは現在であり、また未来のみである」とは、P.F.ドラッカーの名言録の一節である。つまり、「過去の失敗を必要以上に引きずることなく、将来の夢や目標に向けて、これからいかに行動するかが重要である」ということである。
仕事柄多くの経営者、経営幹部とお会いする機会があるが、成功者といわれる方がいらっしゃる一方で、残念ながら成功者とは言い難い方がいらっしゃる。成功者の方々が持っている共通要件の一つにポジティブな未来志向があると思う。
過去の問題原因を追及することよりも、将来の成功を積極的にイメージし、そのために今何をすべきかを考える。常に前向きな発想が行動の原点にあることが、周囲にも好影響を与え、成功を呼び込むことになる。
未成功者のなかには、「将来の成功イメージが重要なのはわかるが、成功するためには何から手をつければ良いのかわからない」という人が少なくない。
そこで参考にしたいのが、「着眼大局、着手小局」という有名な格言である。
囲碁や将棋の世界でよく使われる言葉だが、大局観を持って、そこに向かって序盤を着実に布石していけば勝ちをつかめるという意味で、特に苦しい時ほど目の前の一手に最善を尽くすことが重要であるという意味も含まれている。
では、今着手すべき小局とは何か。
それは「あたり前の事をあたり前にやる」ということではないだろうか。
「なんてあたり前のことを言うのだ!」とお叱りを受けるかもしれないが、この「あたり前の事をあたり前にやる」のは意外と難しく、本当にできている会社は少ないのが現状ではないか。挨拶しかり、5Sしかりである。
自社にとっての「あたり前の事」とは何と何で、「あたり前の基準」とはどのレベルなのかを再確認した上で「あたり前の事をあたり前にやり切る」ことこそが、「大局=将来の成功イメージを現実化する」ための最善策である。
無縁社会
代表取締役社長 石黒仁司
所在不明高齢者問題が大きな社会問題となっている。
きっかけは、東京都足立区で、生存していれば都内最高齢のはずの男性がミイラ化した遺体で発見されたことによる。
その後の調査で次々と所在不明高齢者の存在が判明するわけだが、中には御年200歳、緒方洪庵と同級という超超高齢者まで登場してしまった。
足立区のケースは年金の不正受給を目的とした家族の悪意があって起きたことだが、その他多くの所在不明高齢者問題は、戸籍または住民票といった行政システムの機能不全という側面とともに、世界で高齢化の最先端をいく日本という国の将来的な課題を浮き彫りにしている。
30年後の2040年には、人口の過半数が55歳以上になると推計されている。これは日本という国が「準限界集落」化することで、ドラッカーの言うところの「すでに起こった未来」としてほぼ確定している。発生確実なこの重要課題に対し、社会保障制度など国全体としてどう立ち向かうか真剣に考える時が来ている。
今年の1月にNHKスペシャルで「無縁社会」という番組が放送された。
番組の中で「身元不明の自殺と見られる死者」や「行き倒れ死」といった無縁死が年間3万2000件に及び、日本社会が深刻な「無縁社会」に突入していると報じられていた。
血縁、地縁、社縁などかつては強く結ばれていた縁が高齢化はもとより、核家族化、晩婚化、非婚化、他人との関係の希薄化など様々な問題から途絶え、断絶し「無縁社会」を生んでいるという。
今回の所在不明高齢者問題もこの「無縁社会」化が大きな要因であることは間違いない。
血縁、地縁の断絶もさることながら、気になるのは社縁の希薄化である。
我々社会人は生活面で会社に依存する度合が高い。必然的に会社で形成される社縁が、地縁・血縁より優先されがちになる。かつて自分も含め大多数の社会人は、社会に出てからは社縁を中心に、それを最も大事にしながら生活してきた。
その社縁が非正規社員比率の増加など様々な理由から希薄になっているという。
良しにつけ悪しきにつけ、かつて日本企業が持っていた力強さは社縁の強さ、深さがもたらす連帯感によるところが大きいのではないかと思う。
人間は社会的な動物だと言われる。社縁という他者との前向きなコミュニケーションがなければ連帯感も生まれることはなく、モチベーションも低下する。
今後、社縁の復活が必要と考えたとき、企業が一つのコミュニティとして機能し、メンバーの社会的・感情的な欲求を満足させるという側面からの組織づくりを検討する必要があるのではないか。
日本人らしさ
代表取締役社長 石黒仁司
知人の紹介で「宮司が語る京都の魅力」という書籍に出会った。著者は、京都の恵美須神社第37代宮司の中川久公氏である。
『年間5,000万人もの観光客を魅了して止まない京都の魅力は一体どこから来るのか、様々な伝統行事のルーツを遡りながら探る一冊。知れば京都がもっと楽しくなる!きっと誰かに話したくなる、身近な行事の意外な由来』
と出版社では紹介されているが、読んでみると京都の紹介というよりも、伝統行事や習慣の解説を通して、日本人特有なものの考え方、心のあり方のルーツについて説明されている。折しも、W杯南アフリカ大会での日本代表の快進撃に、「日本人らしいサッカーが世界の強豪を震撼」「日本人的団結力」「日本人として誇りに思う」など“日本人”という単語を目にし耳にする機会が多く、『日本人らしさとはなんだろう?』と疑問を感じていたところだったので、興味深く読ませていただいた。
本書では、「現在まで受け継がれる伝統を培った繊細な心と、すべての生命の尊厳に対する敬意が日本人が本来持っている特質であり、精神構造の基礎である」という事が、様々な祭りの起源や言葉の本来持っている意味の解説を通してまとめてある。
例えば、「いただきます」は、他の生命をいただく(食する)ことでしか、自らの生命を維持できない存在である人が、その命をいただくことに感謝する挨拶として「生命をいただきます」という意味であって、食事や素材を作ってくれた人への感謝では本来ないのだそうである。 『最近は学校給食のときに「いただきますと子供に言わせるな」とクレームをつけてくる保護者がいるという。給食費をちゃんと払っているのだから誰に感謝する必要もないというのだからなげかわしい』と著者である中川氏は失われゆく日本人の心を憂慮している。
また、日本人が特別な思いを寄せる「さくら」について名前の由来が解説されている。 さくらとは「サの神」の降りてくる場所という意味で、「サ」とは田作りの神であり、「クラ」とは神の依るところであり、さくらの開花が田植えの合図となっていたという。 古来、日本人は樹木や岩といった「しるし」に降りてくる神々を「見立てる」ことによって祀っている。 『「見立てる」とは、見ることを積極的に行うことで、見ようとしなければ決して見えないものであり、自らが神を積極的に感じなければ、何も生まれてこない。この事こそが日本文化の核心であり、日本人の心に内在する核となるものである』と著者は述べている。
サッカーの世界でもそうだが、「日本人は創造性に欠ける」とよく言われるが、本当だろうか。
祖先が持っていた「見立てる」能力とは、まさに創造力であり、昔の日本人は素晴らしい創造性を持っていたのではないか。それがいつの間にか「自らが感じ、生み出す能力」を封印してしまい、本来、心の核として存在するはずの創造性をどこかに置き忘れてきてしまったのではないか、などと自己反省させられる名著だった。
「伝える」と「伝わる」の溝を埋める
代表取締役社長 石黒仁司
日本生産性本部の「職業のあり方研究会」より、平成22年度の新入社員のタイプが発表された。本年度は「ETC型」と命名されている。解説によると「ETC型」とは、
性急に関係を築こうとすると直前まで心の「バー」が開かないので、スピードの出しすぎにご用心。IT活用には長けているが、人との直接的な対話がなくなるのが心配。理解していけば、スマートさなど良い点も段々見えてくるだろう。"ゆとり"ある心を持って、上手に接したいもの。
となっている。
ここで気になったのが、ETCによってドライバーと徴収員との対話がなくなったように、効率性を重視するあまり人との直接的なコミュニケーションが不足することが危惧されるというくだりである。これは、本年度の新入社員の特徴という訳ではなく、社会全体に言えることではないかと思う。
読売新聞の民主党に関する特集記事のなかでは、次のようなことが書かれていた。
ひとつが、原口総務相の愛用するツイッターでの出来事。
ご存じの通り、ツイッターとは140文字以内のつぶやきをネット上で世界中に発信できる簡易投稿サイトである。
原口氏はツイッターで総務省の課長を名指しして「アレンジよろしくお願いいたします」と関係者との面会を設定するようにつぶやき、当の課長も「承知いたしました。大臣にツイッターでご指示いただける時代になったとは。感慨深いです」と反応したと言う。
半ば衆人環視の状態で行われた課長への指示に他のフォロワーから「指示は役所の中で、きちんとお願いします」と注意の書き込みがされたそうである。
もうひとつが、鳩山政権がネット上で官僚からの政策提言を募った「政策グランプリ」での出来事。
232件の応募があったそうだが、局長や審議官からの応募もあったと言う。
「いつも顔を合わせている局長が、大臣に直接意見を言わず応募すること自体、今の政と官の関係を象徴している」と多くの官僚が嘆いている。
この二つの事例は「政治主導」という鳩山政権にとっての効率性を重視するあまり、官僚の声に耳を貸さず、官僚側も距離を置くといった直接的な対話不足の例であろう。
結果、政と官、ましてや政権内でも意思疎通がはかれずに諸々の問題が噴出しているのは周知のとおりである。
ツイッターだけでなく、メール、SNS、ブログなどインターネットを活用したデジタルなコミュニケーション手段は、生活していくうえで必要不可欠なものであることは疑う余地がない。デジタルなコミュニケーションは「伝える」ためには大変便利で効率的なツールである。
ただし、真意が「伝わる」かというと、伝達者の技量にもよるが、非常に難しいのではないか。こちらは伝えたつもりでも、それは伝わっていなかったというケースがデジタルコミュニケーションでは多く発生する。
真意を伝え、本当の意味で意思疎通をはかるためには、直接的な対話の中で、表情、しぐさ、しゃべりのトーンなど含めたアナログなコミュニケーションが重要となる。
「伝える」と「伝わる」の溝を埋めるためには、一見非効率ともとれる対話を軸とした、アナログなコミュニケーションを新入社員だけでなく、我々先輩社員ももう一度見直す必要があるのではないか。
事業承継は偉大な経営者となるための
最後のテストである
代表取締役社長 石黒仁司
先日、日経流通新聞に「好調ユニクロ、後継者育成が急務」と題する記事が掲載されていた。
今年2月に柳井氏とともに05年秋から社内取締役を務めてきた松下正氏が辞任した結果、ファーストリテイリングの社内取締役は柳井氏1人となってしまった。取引先企業からは「結局は柳井商店だった」と受け止める声も出た。
この問題は柳井氏本人も重々承知しており、躍進に必要なのはもはや外部の力ではなく、企業理念を理解し実践できる内部の人材だと腹をくくったようだ。これを裏付けるかのように、柳井氏は社内向けの年頭訓示で「5年で大量の経営者を育成する。10年間で一人前の経営者に育成し世界中のグループ事業で活躍させる」と宣言した。3年間で経営幹部候補生200人を集中育成する方針だ。
「世界一」のカジュアル企業になるとの目標実現のためにも、ユニクロをここまで発展させた手腕を人材育成でも発揮することが不可欠だ。
(2009年4月3日 日経流通新聞抜粋)
柳井氏のカリスマ性が成長の原動力であったと言っても過言ではないファーストリテイリングにとって、事業承継、特に経営の承継は今後を占う上で最も重要で、かつ、最も難解な課題と言えるだろう。
「事業承継は偉大な経営者となるための最後のテストである」とはP.F.ドラッカーの言だが、柳井氏も最後のテストに向けて猛烈な受験勉強をスタートした、といったところであろうか。
事業承継支援はMELのコンサルティング事業の柱だが、一口に事業承継といっても百社あれば百通りの事業承継課題が存在する。
そんな百社百様の事業承継において、一つの真実として我々が確信していることがある。
それは「後継者は身内がイチバン」だということである。
先の新聞記事の中で「躍進に必要なのはもはや外部の力ではなく、企業理念を理解し実践できる内部の人材だ」という件があるが、まさに事業承継とは、その企業の理念および事業に対する思い、夢、ミッションを熱く、正しく後継者に伝えることが出来るかどうかが成否を分ける。ただし、企業理念や夢、思いは形のないものだけに、それを正しく伝えることは非常に難しい。それを語らずとも自然に感じ取ることができる存在が「身内」であり、それが「身内がイチバン」だという理由にほかならない。
勘違いをしていただきたくないのは、ここで言う「身内」とは、必ずしもイコール親族ということではない。
もちろん親族であることのアドバンテージはあるが、それよりも企業理念に共感し、「事業に対する思い」「夢」「ミッション」で紡がれた強い絆を共有している人間をここでは「身内」と呼んでいる。
社内に「身内」が育っていますか?
最後のテストの第1問目である。
事業承継書籍のご案内
江戸しぐさ
代表取締役社長 石黒仁司
少し前の話になるが、公共広告機構がテレビで「江戸しぐさ」のCMを流していたことがある。
男性が道を譲ってくれた女学生の脇を通り抜ける際、顔を向けて帽子をちょっと取るようにしながらにこっと御礼をしているように見える「会釈のまなざし」や、電車で腰の両側にこぶしをついて軽く腰を浮かせ、少しずつ幅を詰めながら1人分の空間を作る「こぶし腰浮かせ」などが紹介されていたのを覚えている方も少なくないのではないか。
他にも、狭い道ですれ違う時、肩を引き合って胸と胸を合わせる形で通り過ぎる「肩引き」や、雨のしずくがかからないように、傘をかしげ合って気配りして往来する「傘かしげ」などが紹介されていたのを記憶している。
地下鉄の中吊りなどでも紹介されており、ちょっとしたブームになっていた。
「江戸しぐさ」と聞くと、礼儀作法やマナー動作などのパフォーマンスのことと思われる方が多いようだが、パフォーマンスはその一端に過ぎず、実態はもっと奥深いものである。
越川禮子さんの著書「江戸しぐさ」によると、「江戸しぐさ」とは、日本における江戸期の商人の生活哲学・商人道であり、しぐさは仕草ではなく思草と表記する。もともと商人(あきんど)しぐさ、繁盛しぐさといわれ多岐にわたる項目が口伝により受け継がれたという。商家に伝わる門外不出の未公開の処世術であり、倫理観、道徳律、約束事ともいうべきものである。
しぐさを思草と表すように「江戸しぐさ」は、江戸商人のリーダーたちが築き上げた行動哲学である。よき商人としていかに生きるべきかという商人道であり、同時に、万民に役立つグローバル・スタンダードとして通用する江戸の感性でもあった、と解説されている。
その中にこんな一節がある。
「この人と会うのが、自分の一生でただ一度と思えば、人は誰でも真剣になるはずだ。一見のお客様をも相手にしなければならない商人ともなればなおのこと。この一期一会の気持ちから出発するのが「商人しぐさ」「繁盛しぐさ」、つまり「江戸しぐさ」なのだ。江戸の商人は一期一会の精神で客に接することを信条としていた。
「この客は、もう二度と暖簾をくぐることはないだろう」といった考え方で、残り物や粗悪品を売りさばく。こんな不様は決してしなかった。いったん信用をなくすと、もう商売できないのが江戸商人の掟だ。つまり江戸払いになる。商人が江戸を追われることは死を意味したのだ。」
昨今、連発している不祥事だが、またも食の世界でとんでもない事件が発生してしまった。張本人の社長は謝罪の中で「このような大事件を引き起こしたことは万死に値する。」と宣うたが、まさに倫理感、道徳律を欠いた、商人道からは遠く外れた所業であり、「江戸しぐさ」的にも、万死に値する行為であろう。
前述の著書の中で、越川禮子さんは「江戸しぐさは、日本人の血の中に流れているアイデンティティーそのものである。日本人が日本人のアイデンティティーを失ったら、行く先、日本人として生きていくことが難しくなるのではないか。特に、上に立つ者たちが、何か大事なものを見失っている気がしてならない。」という危機感を訴えていらっしゃる。
我々、現代の企業人として、商人道から外れてはいないか、日本人としての感性を失っていないか、何か大事なものを見失っていないか、自分自身の「しぐさ」を見直す必要があるのかもしれない。
私どもエム・イー・エルでも、現代の日本人に不足しつつある「やさしさ」、「おもいやり」、「勇気」、「協調性」などのEQ(感情知能指数)能力を高めるためのプログラムを展開している。企業や社会に対して、大きなダメージを与えつつある、日本人としての感性の欠如を、EQ能力という側面から診断、向上を目指すという取り組みである。
詳しい内容は当HPのオピニオン欄に掲載されている、「EQを活用して人間力UP!」をご覧いただきたい。
体幹を鍛える
代表取締役社長 石黒仁司
先日、不覚にも急性腰痛症、いわゆるギックリ腰になってしまった。
特に重いものを持ったわけでもなく、少し無理な姿勢をとっている時に咳をしただけで、腰に激痛が走り動けなくなってしまった。
痛みに耐えられず、医者に掛かった時に言われたことだが、原因は日頃の運動不足にあるので完治後はよく体を動かすように、との忠告を受けた。
ただし、ただ闇雲に運動をすればよいわけではなく、「体幹」を鍛えることを意識した運動を薦められた。
体幹とは、背骨と骨盤など身体の中心軸であり、これらの周りにある筋群を体幹筋と言う。
強く安定した体幹は、力の出力の増加、神経−筋効率の向上、オーバーユースによる傷害の減少に大きく関与している。これは四肢の大きな筋が体幹とつながっていることが関係しており、すべての動作において体幹が軸、土台の役割を果たしている。
体幹を鍛えることを疎かにし、四肢の強化をしたところで、軸を持たない四肢はその力を最大限発揮することはできないし、障害を生む要因となる。
体幹部がしっかり安定すると、四肢の動作もスムーズになり、エネルギーの伝達も効果的に行うことが可能となり、持てるパワーをフルに活用できるようになる。
スポーツの世界でも、一流と言われるアスリートは、この体幹を鍛えることにトレーニングの大半を費やしている。
同じことが企業体にもあてはまるのではないか。
企業における体幹とは、言うまでもなくトップの持つ理念であり、将来に対する明確なビジョンであろう。そして、それを支える体幹筋が人材育成ということになる。
企業の体幹である、理念・ビジョンを強く打ち出すことなく、場当たり的で近視眼的な経営を行っているうちは、組織が効果的に機能することはなく持てるパワーも分散してしまう。
また、体幹筋である人材育成を怠り、小手先の改革やシステム構築で経営革新を実行しようとしても成果を得ることはできず、逆に障害を生む要因にしかならない。
自社の成長の土台、基軸となる理念・ビジョンを明確化し、組織の隅々にまで浸透させ、実直に実践することが、企業における体幹を鍛えるということであろう。
また、そのために必要な人材像を明確にした上で、理念を実践するため、ビジョンを達成するため、という視点で人材育成を続けることが、体幹を安定させるための体幹筋強化ということである。
熾烈さを増し、不連続な変化が常態化する経営環境において、変化に耐え切れず厳しい対応に迫られる企業が少なくない。しかし、体幹を鍛え続け強化されている企業は、逆風をものともせず力強く成長を続けている。
是非、体幹を鍛え、体幹筋強化のトレーニング方法を見直すことで、変化に負けない強い会社を創り上げたいものである。
正直の徳
代表取締役社長 石黒仁司
NTTドコモとKDDIが、携帯電話の基本使用料が半額になる料金プランを「いきなり半額」と強調して表示したチラシが、景品表示法違反(有利誤認)にあたる恐れがあるとして、公正取引委員会は16日、両社に警告した(平成19年11月17日 読売新聞)。
このチラシだが、「半額」の文字はKDDIが約5センチ四方、ドコモが約7センチ四方の活字を使っているのに、「2年間の継続契約が必要で、途中解約すると解約料の9975円が発生する」という注釈の文字は約2ミリ四方の大きさだった。
読売新聞の解説では、「このチラシは月額基本料半額の文字ばかりが目立ち、解約料など消費者の不利益になる点を隠そうとしているとしか思えず、顧客にしっかりとサービス内容を説明しようと言う意識に欠け、顧客軽視と批判されても反論できないだろう。」と強い調子で批判している。
今回のケース以外でも、「その事は契約書に記載されてます。しっかり確認しなかったあなたが悪いのです。」的な、購買に当たって顧客が判断ミスを犯すことを期待しているのではないか?と疑いたくなるようなアプローチで商売を行っている業界が少なくないような気がする。生保・損保各社で発生した保険金不払い問題なども、複雑でわかりにくい契約によって顧客の判断ミスや未請求を誘い、ある面、弱みにつけ込んで、顧客の不利益などお構いなしに自社の利益確保を優先させた結果が生んだ不祥事と言えるだろう。
最近、江戸時代の倫理学者、石田梅岩の「石門心学」という思想が、日本のCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)の原点とも呼ばれ再評価されている。
その思想とは、神道・儒教・仏教の三教合一説を基盤としており、その実践道徳の根本は、天地の心に帰することによって、その心を獲得し、私心をなくして無心となり、仁義を行うというものである。その最も尊重するところは、正直の徳であるとされている。
また、「士農工商」の封建社会にあって、広く庶民に「商い」の基本を説き、当時蔑まれていた商人の営利活動を「商人が利益を得るのは、武士が禄をもらうのと同じ」と述べて、商行為の正当性を主張し、商人にプライドをもたせる教えでもあった。
石田梅岩の教えからすると、「正直の徳」と「営利活動の正当性」はお互いが高いレベルでバランスすべきものであり、この二つのバランスを欠いたのが前述のケースであろう。
ぜひ今一度、石田梅岩が売利の本質として説く、「実の商人は、先(相手)も立ち、我(当方)も立つことを思うなり」「商人は二重の利を取り、甘き毒を喰らい、自ら死するようなことをしてはならない」という言葉の意味を確認する必要があるだろう。
また石田梅岩は、「仁(他人を思いやる心)」、「義(人としての正しい心)」、「礼(相手を敬う心)」、「智(知恵を商品に生かす心)」という4つの心を備えれば、お客様の「信(信用・信頼)」となって商売はますます繁盛するのだと孔子の五常の徳を用いて商売の本質を説いている。
つまり、企業本位の目先の経営はいづれ行き詰る。真の顧客本位の倫理観を持った企業のみが生き残るということであろう。
最近の企業本位な姿勢から続発している、さまざまな不祥事を見るにつけ、我々企業人、特に経営者の社会的責任はさらに重く大きなものとなっていくと感じる。改めて、石田梅岩の説く「正直の徳」を再確認する必要があるのではなかろうか。
生物と無生物のあいだ
代表取締役社長 石黒仁司
講談社現代新書から発刊されている「生物と無生物のあいだ」(福岡伸一 青山学院大学教授著)がベストセラーになっている。「生命とは何か」という生命科学最大の問いに、分子生物学の見地から考察を加えるという趣旨の本である。
この本が秀逸なのは、普通この手の科学書は、専門用語ばかりでなに言っているのかわからん!と私のような門外漢は興味はあれど敬遠しがちだが、歴史の闇に沈んだ天才科学者たちの逸話などを紹介しながら、実に表現力豊かに現在形の生命観が語られていく。
「ページをめくる手がとまらない極上の科学ミステリー。分子生物学がたどりついた地平を平易に明かし、目に映る景色がガラリと変わる!」とは講談社による紹介だが、本当に面白く読み応えのある本だった。
結論としては、「生命とは自己複製するシステム」である。このことは生命を定義づける鍵概念であることは間違いないとしながらも、我々の生命観には別の支えがあるとして、「生命とは動的平衡にある流れである」と定義している。
「生命という名の動的な平衡は、それ自体、いずれの瞬間でも危ういまでのバランスをとりつつ、同時に時間軸の上を一方向的にたどりながら折りたたまれている。それが動的な平衡の謂いである。それは決して逆戻りできない営みであり、同時に、どの瞬間でもすでに完成された仕組みなのである。」
つまりは、生命とは代謝の持続的変化であり、この変化こそが生命の真の姿であり、やわらかな適応力となめらかな復元力をもつ、ということだろうか。
また、文中に「すべての物理現象に押し寄せる”エントロピー増大の法則”に抗して、秩序を維持しうることが生命の特質である」という過去の学者の定義が載っている。エントロピーとは乱雑さ(ランダムさ)を表す尺度で、すべての物理学的プロセスは、物質の拡散が均一なランダム状態に達するように、エントロピー最大の方向へ動き、そこに達して終わる。これをエントロピー増大の法則と呼び、生物の死も、生命というシステムの死でありエントロピーが最大となった状態を言うそうである。
「生物が生きている限り、エントロピー増大の法則は容赦なく生体を構成する成分にも降りかかる。高分子は酸化され分断される。集合体は離散し、反応は乱れる。タンパク質は損傷を受け変性する。」そして、それを放って置けば、エントロピーは最大となりやがて死に至る。生命は、死に至らしめない方法として、やがては崩壊する構成成分をあえて先回りして分解し、乱雑さが蓄積する速度よりも早く、常に再構築を行う。このことが代謝の持続的変化であり、そうすることで、エントロピー増大の法則に抗うことになり、生命の秩序が保たれることになる。
企業もある種、生命体だととらえることは珍しくないが、最近では代謝の持続的変化が行われずに生命の危機に瀕している企業が続出している。
不二家の期限切れ原材料使用問題、石屋製菓の賞味期限先延ばし問題、赤福の消費期限及び製造日・原材料表示偽装問題など、まさに「死に体」となってしまうケースが後を絶たない。これらの企業は代謝することを忘れ、過去からの悪しき習慣という乱雑さの蓄積を分解・再構築することなく、悪いことだと気づいていたものの、そのまま放っておいた結果、エントロピーが最大となり、ついに最悪の結果を招いてしまった。悪しき習慣という乱雑さを早いタイミングで分解し、新たな習慣を再構築し、企業生命の秩序を立て直す勇気が欠けていた結果であろう。
老舗と呼ばれている企業に今回のような問題が起きてしまった一つの原因として、代謝の持続的変化、エントロピー増大の法則に対する抵抗が、長い社歴の間に衰えてしまったことがあげられるのではないか。企業を取り巻く環境の流れは、過去には想像もできなかったほど早くなっている。当然、流れのスピードにあわせ代謝のスピードも早めなければ生き残れない。過去の流れにあわせた代謝を現在も行っている、または代謝そのものが出来なくなってしまった企業は必然的に淘汰されるのである。
環境の流れの速さを見極め、ハード、ソフト、そしてハート面の構成要素をあえて分解し、再構築をし続けることが企業存続にとって必要不可欠なことだとも言えるのではないか。
モスキート音
代表取締役社長 石黒仁司
昨年から若者の間で、モスキート着信音なるものが流行しているという。
携帯電話の着信音に17キロヘルツという高周波数のブザー音であるモスキート音を設定する。すると高周波数の音は年齢とともに聞きにくくなるため、おおむね20代後半以降の大人にはほとんど聞こえないが、10代の若者には「ブーン」という蚊の羽音のような着信音が聞こえるらしい。
授業中にこっそり「モスキート着信音」を鳴らし、教師が気づくかどうかを試す遊びがはやっており、まさしく“大人の知らない世界”を満喫しているそうだ。
もともとは、英国の会社が「モスキート」の商品名で、店頭や駐車場などでの迷惑行為をする若者を排除したり、店内に長く居座っている若者客を店から追い出すため、若者にしか聞こえない不快音を発生させる若者撃退商品として開発したものだが、想定外の利用方法で若者の間で流行してしまったらしい。
大人には聞こえないが、若者には耳障りなモスキート音。
周りに選挙期間中の選挙カーのごとくモスキート音を撒き散らす大人はいないだろうか。本人には聞こえないだけに発しているという自覚はなく、聞かされている若者は不快極まりなく、コミュニケーションの溝は深まり、モチベーションは下がりまくる。
大人:「今の若者は覇気がない。昔はすごかったぞ。俺たちが君ぐらいの年齢のときは、よく上に意見したもんだよ。君も言いたい事があったら、怖がらずに意見を言いたまえ。」
若者:「ハァ。(この前、実績も上げていないのにエラそうなこと言うな、って・・・)」
リッパなモスキート音である。
理解や納得を得るには、相手の心に届く音を発信する必要がある。心に届く前に耳で拒絶されてしまっては、届けなくてはならない音も決して届くことはない。相手の心にダイレクトに響く周波数は何キロヘルツなのか。
今の周波数は高すぎる(高圧的)のか低すぎる(迎合的)のか。改めてコミュニケーションの周波数をチューニングして、心に届く聴きやすい音を奏でる努力が必要である。
ただしこのチューニングだが、なかなか同調させるのは難しい。同調させるためには、相手のもっとも聴きやすい周波数を探り当てる必要がある。ではチューニングに必要なこととは何か。まず相手の話を聴くこと、つまり傾聴である。 何を考え、何に悩み、どんなことに喜びを感じるのか、これらは聴いてみなければわからない。わからない限り周波数が相手と同調することはありえない。 ぜひ、積極的に「聴く」ことからコミュニケーションの改善をはかりたい。
最後に「聴く」ために最低限必要なことは、
・話を聴くときは相手と目線を合わせる
・相手の話をさえぎることなく最後まで聴く
・意見やアドバイスは相手が求めた時だけ
というのが、基本中の基本になっている。
この3項目を実践するだけでコミュニケーションの溝は大幅に埋まり、心の蚊帳も外すことができるのではないか。